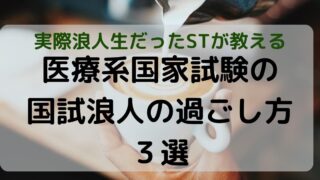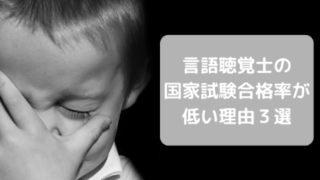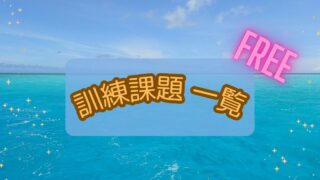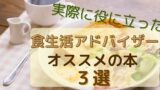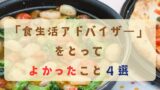よくST業界で言われているのが、
「STは学校で全く栄養面の勉強していないけれど、
栄養面も分かればいいのに」という話が上がります。
それは、病院でも訪看でも栄養は大事ですね。
キッカケ1:NSTに入るうえで栄養の基礎の基礎を知っておきたいから
トメは働いている病院にNST(栄養サポートチーム)導入前に
訪問看護に転職してしまったのですが、
もし、今病院に転職するならNSTのある病院に転職するかもしれない…
と思ったので、
比較的簡単で栄養面の基礎を学べる「食生活アドバイザー」を取っておこうと思いました。
もちろん、「食生活アドバイザー」を取ったからと言って、
必要な栄養素の計算ができるわけではありませんし、
患者さんそれぞれの体調管理までできるわけではないのですが
それでも栄養の基礎だけでも今のうちに勉強しておこうと思ったのが
トメトメが「食生活アドバイザー」をとろうと思ったキッカケです。
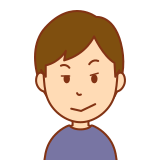
そんな知識、
NSTに必要じゃないよ

まぁ正直そんなにNSTに使わなくても
基礎だけでも学んでおきたいなー
ぐらいの軽いキッカケだったにゃ
キッカケ2:訪看では食事の相談を受けるから
訪看では患者さんのお食事はご家族が用意されることが多く、
在宅での介護環境では、
患者さんのご家族は栄養面のアドバイスを栄養士さん・管理栄養士さんに
気軽に相談する場面は少ないのです。
そして、言語聴覚士は食形態のアドバイスを
するので、ご家族には栄養も知っていると思われちゃって
栄養面での相談を受けることもしばしば…

最初は「わかりません」って答えてたんだけど、
次第にもっと役に立ちたいなーって
思ったんだにゃ
キッカケ3:プライベートでも使えるから
プライベートの理由1:家族・親戚に糖尿病患者がたくさんいる
トメトメの親戚には糖尿病が多く、
予防方法など栄養面の興味がありました。

将来トメも糖尿病になると思うんだ…(笑)
糖質の量について参考になったのはこの本です。
この本や「ほうれん草と小松菜はどちらが糖質多いんだろう?」とかの
疑問を解決できる本です。食品ごとに糖質の一覧を調べることができます。
また、この本の面白いところは外食の食品の糖質も一覧があるところです。
気になる人はお試しに本屋さんでパラパラ覗いてみてください。
プライベートな理由その2:こどもができた
また、自分にこどもができて、
自分が離乳食や大人向けの食事の他にこども向けの少量のごはんを準備しなくてはならなくなりました。
そこで思ったのが、

え…ほんと何作ればいいのん?
もちろん離乳食の本も買いました。
トメトメが買った本はコチラです。
この「フリージングで離乳食」という本は
赤ちゃんに対する栄養の知識の勉強になって、
時期によっての食形態について勉強になりました。
ただ、
とか悩んだり、食に関する謎がたくさんでてきたのも、
「食生活アドバイザー」の資格をとってみようと思ったキッカケでした。
「食生活アドバイザー」のオススメの本
オススメの本 その1
トメトメが資格取ってから確認したら、
なんだかんだユーキャンの本が一番表もあり、分かりやすかったです。
オススメの本 その2
トメトメが実際に買って読んだ本が
この本は図や表が多いのが特徴です。
ものすごくわかりやすかったです。
オススメの本 その3
看護師の友達が買って貸してくれた本がこちら
トメトメが買った本より詳しく書いてあるのが特徴。
より広い範囲を網羅している感じですね。
なので、まずトメトメが買った本でまず覚えて、
模試を受けてみて、
まだ知識量が欲しいという人はコチラの本を買うのがオススメです。
食生活アドバイザーのオススメの本についてより詳しく書いた記事はコチラ
もっと「食生活アドバイザー」を知りたい人はコチラも読んでみて下さい
トメトメが実際に「食生活アドバイザー」をとってみて良かったことを知りたい人は
コチラも読んでみて下さい